中後期飼育
約2センチになると、病気になっても薬剤が使用できるようになるので、大量死などの危機か
ら脱します。
しかも30℃飼育を続けている限り、そう大きな病気にかかることもありません。
なお、私の飼育では「青水(藻の繁殖した緑色の水)」は一切使用しません。
狭い水槽の少ない水量では、光の当たり方などで藻が異常繁殖して水質を悪化させることが
あるからです。
専用の配合飼料を使用すれば、栄養価の面では取り戻せると考えています。
①水槽での成長について。
金魚の成長は飼育槽の広さで大きく変ります。
当然水槽で飼育するのはデメリットであるのですが、水温を安定的に維持できるメリットもあ
りますし、最終的に60センチ水槽で2匹までの数に抑えれば、それなりに大きく育てることが
出来ます。
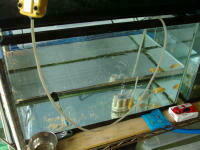
|
写真の様にスカスカに見えるく
らいでちょうどよい。
|
病気などにかかって餌切り(給餌を休むこと)などを1週間も行うと、取り戻すことが出来ない
致命的な成長遅れを作ります。
また、当歳魚でも一旦成長を止めてしまうと、その後の急成長は望めない傾向にあります。
それよりは狭いスペースでも徹底した温度管理をすることで、じゅうぶん成長させることが出
来ると思います。
②飼育数を減らします。(選別)
給餌開始から1週間くらいで、フナ尾と呼ばれている尾の開かない和金みたいな尾をした子
が判別できます。
それをスグに取り除きます。

|
これはひと目でわかります。
(絵が下手すぎ!)
|
さらにそれから1週間後には、尾の開きの悪い子がわかります。
私のつたない経験では、この時点(生後18日前後)で尾の開きの悪い子が、成長に伴って
開いてくる可能性は非常に少ないので、思い切って取り除きます。
出来るだけ真一文字に開いているもののみを残します。

|
迷ったら残さないのが基本で
す。出来るだけ開いた子を残し
ましょう。
(絵が下手すぎ!)
|
さらに1週間後には、尾の左右の中心が重なっているものと、身体全体に左右のバランスが
悪いものがわかります。
これも治る可能性はあまりないと思います。

|
この辺になると、ショップの10
00円らんちゅうではよく見かけ
ます。
(絵が下手すぎ!)
|
生後一ヶ月くらいで、横から見れる水槽のようなものに入れ、横見の選別をします。
これは3つの点をみます。
まず背びれ(他種の金魚に見られる背中から尾にかけてのヒレ)が出ていないかを確認する
必要があります。
らんちゅうと言えども金魚はフナの亜種ですので、代を重ねるとフナに近い体型に先祖がえり
する傾向があり、背びれの飛び出たものが数%発生します。
上からだとわからないことが多いので、この際によく観察します。

|
上から見ると、なかなか気が付
かないものです。
最初のうちは、横からも見まし
ょう。
(絵が下手すぎ!)
|
2番目に同様に背中の凸凹を観察します。
程度の軽いものは肉が付いてわからなくなることもありますが、気になるようなものは選別し
ます。

|
これも横から。
大きな凹みは、成長すると更に
目立ったりします。
(絵が下手すぎ!)
|
最後に尾の付き方を観察します。
理想は背中の曲線が終わったところで90度に立ち上がっていることですが、環境で治ること
もあるので、ここでは垂れ下がって尾が付いているものを取り除きます。

|
チョットだけなら水深を浅くする
と治るそうですが、水平以下の
は見込みありません。
(絵が下手すぎ!)
|
ここでは基礎的な選別のみを書いてあります。
後は専門サイトをご覧になるか、専門書・ベテランの方の指導など参考にしてください。
③60センチ水槽に移します。
全長(尾も入れて)2センチ程度になったら、60センチ水槽に移します。
1水槽当たりに、この大きさで5匹程が限界です。
最終的には2匹までしか入れられず、これ以上入れると極端に成長が遅れます。
それでも水の汚れは激しいので、毎日50%以上の水換えが必要となり、私は必ず80%以
上換えることにしています。
きれいな水は食欲増進にもつながり、成長が促されます。

|
60cm水槽でも、せいぜい10
センチまで。
それ以上大きくする場合は、広
い容器を用意してください。
|
④えさの移り変わり。
色々試しましたが、幼魚期はテトラフィンに代表されるようなフレーク状の餌で十分です。
金魚の口の大きさに合わせて、手でつぶして与えます。
稚魚~全長2センチ時はブラインシュリンプ主体で、3センチになるまでフレーク状の餌、そ
れ以上でらんちゅう専門の超小粒の餌を使い、私の場合面倒なので親魚にも超小粒を与えて
います。
らんちゅう専門飼料は各社から多様なものが発売されていますが、色揚げ(赤みを強くするこ
と)や肉瘤増強(頭のコブの成長を促す)など、飼育目的に合わせて利用します。
赤虫などの生餌・冷凍餌などは、水量の少ない水槽では水の汚れにつながりますので、私は
使わないようにしています。

|
なんだかんだ言って、よく食べ
る餌です。
|
以上、これが私の飼育方法です。
まだまだ通過点で、らんちゅう飼育には正解はなく、いろいろ改善していきたいと思いますの
で、気付いた事があれば掲示板・メールで教えてください。
情報交換で、更に良い飼育方法を見つけましょう。
2004年度版に、乞うご期待!

|